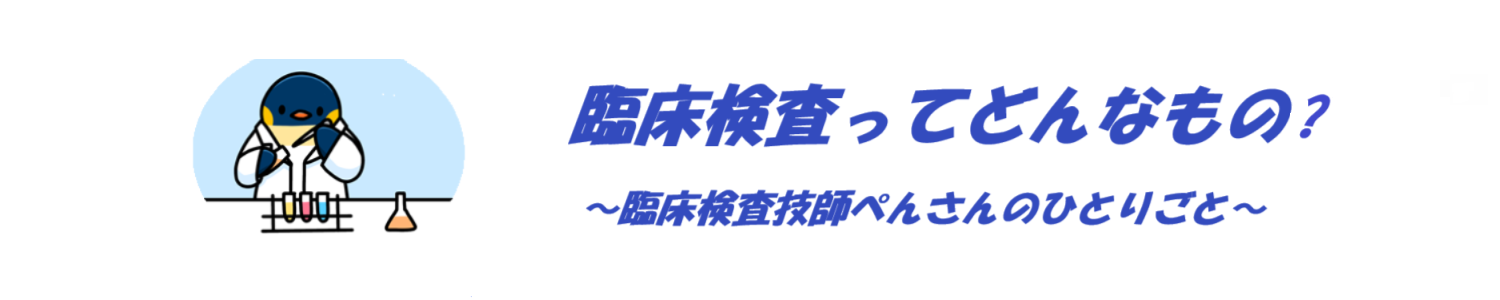臨床検査のことをもっと知ろう
~臨床検査技師ぺんさんのひとりごと~
正確な検査結果のための技術と工夫
「安心」を届けるために

こんにちは ぺんさんです。
当サイトにご訪問いただきありがとうございます。
臨床検査技師としての経験をもとに
検査の意味や検査室での工夫や
臨床検査技師が考えていることなどを
できるだけわかりやすく
お伝えしたいと思っています。
医師との会話や
患者様とお話した経験なども交えて
臨床検査技師の目線で綴っていきます。
お気軽にお付き合いいただけるとうれしいです。
一般の方はもちろん医療に携わる方にも
臨床検査への理解を深めるために
役立つ内容になっていると思います。
病院や健診で検査を受けて
あるいは日常の臨床検査に関わる中で
疑問や不安に思った時などに
ちょっと覗いていただけたらと思います。
はじめての方は
「こんなことがありました」から
読んでみてください。

なお、当サイトで扱っている情報は、
診断や治療を目的としたものではありません。
臨床検査に対する理解を深めていただくための
情報や知識の提供の場であることを
ご理解いただきたいと思います。

新着記事
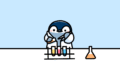
血液学検査2[検査結果のこと6]
血液学検査の中で、凝固検査について取り上げています。凝固検査は「凝固」と「線溶」の機能を調べる検査です。これは「出血」や「血栓」など、生命にかかわる機能を調べる検査ともいえます。健康診断などではあまり馴染みがないかもしれませんが、手術前検査などには必ず含まれている重要な検査です。少し専門的な内容も含みますが、凝固の機序など、一般の方はあまり触れることのない内容でもあるので、是非読んでみていただきたいと思います。
2025.12.24

血液学検査1 [検査結果のこと5]
血液学検査は血算や凝固の検査です。それぞれ項目は多数ありますが、今回は血算、つまり赤血球や白血球の数や形態を調べる検査について解説します。血算は健康診断などでも必ず調べる検査なのでお馴染みの検査だと思いますが、細かい内容についてはなかなか知られていないのではないかと思います。そのあたりをわかりやすく解説したいと思います。
2025.12.222025.12.24

インフルエンザのこと
皆さんに馴染みのあるインフルエンザを取り上げます。インフルエンザについて、知ってはいるけど、正確に理解できているでしょうか。できるだけ新しい情報や、検査の裏事情なども交えて、インフルエンザの概要を説明します。
2025.11.212025.11.27
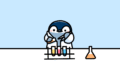
虫卵検査 [便検査のこと3]
寄生虫の感染は、現在では減少傾向にあります。しかし寄生虫がゼロになったわけではありません。海外渡航からの帰国後の体調不良は寄生虫検査の対象となりますし、好酸球増多症などのときも虫卵検査が依頼されます。しかし、検査技師は検査の経験が少なく、検査技術の水準の維持や継承が難しい現実があります。
2025.11.112025.12.08

臨床検査技師への道
臨床検査技師になるにはどうすればよいかについて解説しています。臨床検査技師養成課程のある学校、どのような勉強をするのか、などについて、最近の情報を取り入れながら説明しています。また、どのような人が向いているのかについては、経験をもとに私見も交えながら書いています。
2025.10.192025.11.27
人気記事

溶血の影響 [検査結果の考え方3]
採血検体で溶血が認められた場合は再採血が推奨されます。その理由とともに、再採血ができず溶血検体のまま測定し「参考値」となったときの考え方、注意点などを説明します。
2025.06.102025.11.27
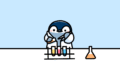
血清情報 [検査結果の考え方4]
生化学検査の報告書などで見る「H・L・I」が示すもの・・・「血清情報(溶血・乳び・黄疸)」について説明します。検査結果を見るときに、この血清情報も合わせて確認することで、より細かい情報を得ることができます。
2025.06.172025.11.27

蓄尿 [尿検査のこと4]
「蓄尿」とは一定時間の尿を専用容器に溜めるものです。通常24時間で行われ、成分の測定を行います。腎機能の評価のためのクレアチニンクリアランス、尿蛋白や尿糖の1日排泄量などの検査に、24時間蓄尿は欠かせません。蓄尿は「ただ溜めるだけ」なのですが、正しく行われずに検査結果が参考値となったり、検査中止となることも少なからずあります。面倒な「蓄尿」ですが正しく理解していただきたいです。
2025.08.192025.12.08

尿定性検査 [尿検査のこと2]
誰でも一度は受けたことがあると思われる「尿検査」。通常「尿検査」というと「尿の定性検査」を意味します。尿の定性検査は、試験紙を使った検査で比較的簡便な検査ですが、たくさんの情報を得ることができ、いろいろな疾患のスクリーニングや補助診断に有用とされています。尿の定性検査につて、検査できる項目や注意点などについて説明します。
2025.07.162025.12.08

検体の溶血 [採血のこと5]
「再採血をする」って結構な衝撃だと思います。なぜ再採血をするのか、その原因のひとつである「溶血」につい考えます。
2025.03.252025.11.27

採血と検査

検体の溶血 [採血のこと5]
「再採血をする」って結構な衝撃だと思います。なぜ再採血をするのか、その原因のひとつである「溶血」につい考えます。
2025.03.252025.11.27

検体の凝固 [採血のこと4]
「再採血をする」って結構な衝撃だと思います。なぜ再採血をするのか、その原因のひとつである「検体の凝固」につい考えます。
2025.03.142025.11.27

再採血 [採血のこと3]
再採血の場面を想定して、なぜ再採血をしなければならないかを解説しています。
2025.03.072025.11.27

採血の注意点 [採血のこと2]
採血する場面を思い浮かべて、一般的に注意したいことを説明しています。大事なことを、その理由を含めてなるべくわかりやすい言葉で説明しました。
2025.02.232025.11.27

採血の大切さ [採血のこと1]
採血は嫌いな人が多いです。でも、採血が必要な場合があります。病院や健診でなぜ採血するのか、について簡単に説明しています。
2025.02.142025.11.27

検体検査とは
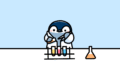
血液学検査2[検査結果のこと6]
血液学検査の中で、凝固検査について取り上げています。凝固検査は「凝固」と「線溶」の機能を調べる検査です。これは「出血」や「血栓」など、生命にかかわる機能を調べる検査ともいえます。健康診断などではあまり馴染みがないかもしれませんが、手術前検査などには必ず含まれている重要な検査です。少し専門的な内容も含みますが、凝固の機序など、一般の方はあまり触れることのない内容でもあるので、是非読んでみていただきたいと思います。
2025.12.24

血液学検査1 [検査結果のこと5]
血液学検査は血算や凝固の検査です。それぞれ項目は多数ありますが、今回は血算、つまり赤血球や白血球の数や形態を調べる検査について解説します。血算は健康診断などでも必ず調べる検査なのでお馴染みの検査だと思いますが、細かい内容についてはなかなか知られていないのではないかと思います。そのあたりをわかりやすく解説したいと思います。
2025.12.222025.12.24

インフルエンザのこと
皆さんに馴染みのあるインフルエンザを取り上げます。インフルエンザについて、知ってはいるけど、正確に理解できているでしょうか。できるだけ新しい情報や、検査の裏事情なども交えて、インフルエンザの概要を説明します。
2025.11.212025.11.27
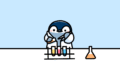
糖尿病の検査 [検査結果のこと4]
糖尿病に関わる検査について説明します。糖尿病は罹る人が多く身近な疾患といえます。健康診断などで指摘されることも多いはずですが、受診に繋がらず放置されるケースも少なくありません。糖尿病は放置すると治療も困難になり、生活の制限も多くなります。血液検査の意義を理解しましょう。
2025.06.272025.11.27

心機能検査 [検査結果のこと3]
心臓の検査は血液検査以外に、心電図、心臓超音波検査、負荷心電図、ホルター心電図、CT検査、MRI検査、心臓カテーテル検査などさまざまなものがあります。診断のためにはいくつもの検査を組み合わせて判断していきます。血液検査だけで心疾患の診断に至ることは少ないかもしれませんが、病状の程度の判定、経過観察などに重要な役割をもっています。心機能に関する血液検査について説明します。
2025.06.272025.11.27